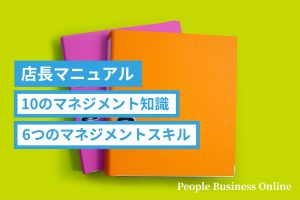店舗監査の重要性:チェーン展開を支える基盤とスーパーバイザー(SV)の役割
昭和中期、米国大手チェーンの日本上陸を機に、国内企業もチェーン展開を加速させました。この動きの中で、労働力確保と人件費削減のため、従業員のパート・アルバイト(P/A)化が大きく進みました。
経営の権限委譲とP/A化の進展
この新しい体制では、正社員である店長やマネージャーが店舗マネジメントを担い、P/Aが接客やオペレーションなどの現場業務を担当する役割分担が確立され、経営の権限委譲が進みました。当時の管理体制は、本社が直接管理する中央集権型と、各店舗に権限を委譲する店舗分権型に二極化しました。
SVによる多店舗経営の統括
特に店舗分権型では、店長が年商1億円規模の店舗経営を管理し、直属上司であるスーパーバイザー(SV)は5店舗、年商5億円規模の経営を統括。さらにSVの上司である統括SVは5名のSVを管理し、合計30店舗、年商30億円規模の経営管理を担いました。これは現在の基準で見れば、SVや統括SVが上場可能な中小企業の経営を担い、その責任に応じた処遇が与えられていたことを意味します。
SVの果たす重要な職務
バブル経済期から現在に至るまで、店舗展開を支えてきたのは、まさにこのSVの存在です。SVは、店舗分権経営の根幹である店舗監査、評価権、人事権、そして予算執行権を適切に行使し、現場を牽引しました。また、経営計画に基づきP/Aを含めた人員の確保・育成、商圏特性と個々のパーソナリティを活かした人員配置によって強い現場を構築し、商圏からの売上と利益の最大化を目指すことがSVの重要な職務でした。
店舗分権経営における多層的な牽制機能と逸失利益の最小化
トータル・マネジメント・システムの概念
店舗経営管理は、商品、施設、労務、人事、防犯、防火、衛生、マーケティング、販促、損益、棚卸ロスなど多岐にわたります。これら全てを連携させた管理は「トータル・マネジメント・システム」と呼ばれます。
SVの決裁権限と経営管理責任
SVは、売上・利益目標の達成、店舗販促、投資と回収、採用・評価・昇格・人事異動といった労務管理、防犯・防火・衛生に関する責任など、経営者と同等の決裁権限と経営管理責任を担っていました。
監査による多重の牽制機能
分権経営が正しく機能しているかを確認するため、人・モノ・金、顧客満足度、安全、犯罪防止、防火、情報、衛生などに関する監査が月に一度の頻度で実施されました。SVの上司である統括SVがSVの監査を、統括SVの監査は内部監査が担当するというように、何重もの牽制機能が働いていました。監査結果は当然ながら、人事評価制度とも連動しています。
健全な経営を実現するスーパーバイジングシステム
この多層的な牽制機能により、逸失利益は最小限に抑えられ、店舗経営ができる店長やSVの育成が進みました。これにより、さらなる店舗展開が可能となったのです。この店舗分権経営によって健全な経営を実現する仕組みは「スーパーバイジングシステム」と呼ばれています。
国内チェーンにおける店舗マネジメントシステムの成否を分けた要因
優先導入された主要システム
「トータル・マネジメント・システム」の導入・構築内容はチェーン店ごとに異なりました。特に、P/Aや正社員の賃金制度と人材開発システム「キャリアパスプラン」、人件費の変動費化「ワークスケジュール」、店舗損益管理「P/Lコントロールシステム」などが優先的に導入され、少数の正社員と多数のP/Aによる店舗経営が一般化しました。
SV経営管理の落とし穴
各店舗の経営管理はSVが担うようになったものの、このSVの経営管理のあり方が企業の成否を分ける結果となりました。多くの企業が中央集権型経営を採用しつつも、顧客満足度測定、人材開発、労務管理、販売促進、損益管理といった運用を店長やSVに権限委譲しました。しかし、ここに大きな落とし穴がありました。
実際の権限委譲は名ばかりで、予算執行や人事評価、店舗会計・業務監査などには本社本部の稟議承認が必要なケースが多く、SVからの報告を受けた本社が承認や決裁を行う内部統制に留まっていました。この結果、対応の遅延、上司への説明や説得を目的とした業務の増加、納得できない人事評価などが横行し、現場の士気や顧客満足度が大きく低下し、人的問題を誘発しました。
機能不全が招いた負の連鎖
人的問題による退職者が増える一方で、採用は進まず人手不足に陥り、オペレーションは崩壊し、不安定な店舗運営がクレームを誘発。SVや店長はいつの間にか問題処理係となり、本来の業務ができなくなり、事態はさらに悪化しました。
主な要因は、経営権限(評価権、人事権、予算執行権)の委譲が不十分だったことです。店舗は「任せ放し」の状態で、業績悪化時には場当たり的な販促やコストカットで一時的にしのぐ対応が繰り返されました。これらは短期的には効果があるように見えても、長期的には大きな損失につながります。
このような場当たり的な対応を繰り返す要因の一つに店舗監査が機能していなかったことが挙げられます。店舗監査が機能しないと、売上低迷、モラル低下、問題の誘発、離職者数の増加、内部・外部不正の横行を招き、利益も現金も失われます。結果として現場は荒廃し、業績は悪化、リストラによる縮小均衡に陥り、経営危機を招いてきました。つまり、企業にとって最も恐ろしいのは、内側から壊れていくことなのです。
景気に左右された利益確保対策の逆効果と店舗監査の必要性
中央集権化への回帰とその影響
バブル崩壊やリーマンショックといった厳しい経営環境下で、多くの企業は利益確保のためにSV制度を廃止し、高給取りのSVを解雇して本社本部による中央集権型経営を推進しました。
その結果、店舗の人手不足対策として労働力確保を正社員に依存したため、社員は「店番」的な存在となり、大きく士気を低下させました。売上増大や利益獲得といった創造性や達成感のあるダイナミックな仕事ができなくなり、単純作業の繰り返しという業務内容になったことで、仕事の魅力が失われました。
キャリアパスプランの形骸化と人材流出
さらに、仕事内容と評価を給与に反映させるキャリアパスプランも形骸化し、努力の有無に関わらず評価も賃金も変わらないため、従業員満足度も大きく低下しました。
このような状況に加え、景気低迷や増税、社会保障費増大などから将来不安につながり、成長意欲のある有益な人材が他業種に流出するなどしてしまい、現在の厳しい状況に陥ってしまったとも言えます。
現代における店舗監査の不可欠性
現代のチェーン展開において、店舗監査は不可欠な要素です。かつては、店長やSVに大きな権限が委譲され、彼らが店舗経営の根幹を担い、多層的な監査体制と人事権の適切な行使により、人材育成、最適な人員配置を通じて現場を強化し、売上・利益の最大化を追求することで企業全体の成長を支えていました。
しかし、店舗監査が機能しなくなると、業績悪化、内部不正、離職者の増加といった問題が連鎖的に発生し、企業は危機に陥ります。店舗監査は、単なる監視ではなく、「人」の健全な成長と店舗、企業の持続的な発展を支える、極めて重要な経営管理システムなのです。
まとめ:本記事の要点と次回への展望
店舗監査は、店舗経営の健全性を保ち、企業の持続的な成長を支える上で不可欠な経営管理システムです。本記事では、過去の多店舗展開における店舗分権経営の成功と、監査機能不全が招いた危機的状況を振り返り、現代において店舗監査がいかに重要であるかを解説しました。
次回記事では、この店舗監査の必要性をさらに深掘りし、「店舗監査マニュアル 2.店舗監査の必要性|店舗経営の核心!売上と信頼を盤石にする監査戦略」について詳しく解説していきます。ぜひご覧ください。