【この記事で分かること】
今、あなたの店舗は大丈夫?消費期限偽装から紐解く、信頼を築く経営の極意。
ミニストップの一部店舗で発生した消費期限偽装は、フランチャイズ経営に潜む構造的な問題があるのではないでしょうか。「作り置き」ではなく、「予約販売」や「ツーオーダー」などのロス削減モデルを導入し、SVや品質保証部が加盟店の経営指導を徹底することが重要です。本部と加盟店が「共存共栄」の関係を築くことで、顧客からの信頼を守り、オーナーが報われる道が開かれることで、更なる発展が期待できます。
信頼の危機、他人事ではない
店舗経営者の皆さん、今回は非常に胸の痛むニュースから話を始めます。コンビニチェーンの「ミニストップ」で、おにぎりや総菜といった店内で調理する商品の消費期限を偽って販売していたことが発覚しました。特に発覚した店舗の多くが関西に集中しているというこの報道は、決して他人事ではありません。
食品には美味しく食べられる「賞味期限」と、安全に食べられる「消費期限」があります。消費期限はそれを過ぎると衛生上の問題が生じる可能性がある日付であり、法律で定められた厳格なルールです。しかし、昔は「期限なんか匂いを嗅いで自分で判断しろ」という”常識”も通用していた時代があり、それがかえって今回の偽装のような不正に繋がる温床となっているのかもしれません。
なぜ偽装は起きたのか? 儲からない“店内調理”とフランチャイズの構造
今回の偽装が発覚したのは、すべてフランチャイズ店舗でした。おそらく、本部直轄の直営店では発生しない事案だと推測します。
フランチャイズは、オーナー経営者が本部の指示に“忠実に”したがって店舗を運営し、そのノウハウと引き換えに「ロイヤリティ(手数料)」を支払うビジネスモデルです。黎明期ならともかく、今はコンビニ同士の競合も厳しく、利益を出すのが大変なのは傍から見ていても分かります。
特にミニストップの“売り”である「店内調理」は、お客さんの期待に応える一方で、実は構造的に儲けにくいという実態があります。小売店やコンビニエンスストアという業態では、店内調理の揚げ物、おでんや肉まんなどは粗利益を確保しやすい一方で、おにぎりや弁当は、調理する人件費がかかり、廃棄ロスなどから儲かりにくい一面もあります。
そこに本部へ献上するフィーが負担としてのしかかってくると、オーナー経営者や現場スタッフは、次第に追い詰められていきます。
現場に忍び寄る「悪魔の囁き」、見逃された不正のサイン
過度な利益追求のプレッシャーに晒され、目の前の経営状況をなんとかしようと模索する中で、見えない「悪魔の囁き」が聞こえてくるのではないでしょうか。
それは、以下のような思考のプロセスだったのかもしれません。
 店舗担当者
店舗担当者本来なら値引きや廃棄をしなければならない商品も、食べるには問題ない(はず)。
 店舗担当者
店舗担当者商品に貼ってある価格シールに消費期限が印字されていて、時間が過ぎるとレジを通らない。それなら…。
こうした思考から生まれたのが、以下の二つの手口だと考えられます。
 店舗担当者
店舗担当者本来のシールの上に、消費期限の長いシールを貼っちゃえ!
 店舗担当者
店舗担当者作った時点より、時間が経ってからシールを貼ろう、そうすれば商品の寿命が延びる!
このような安易な不正行為は、今やスーパーでも通用しません。もしそんなことをしたら、パートさんやアルバイトさんの格好のSNSネタになり、一気に世間にバレて「終了確定」です。
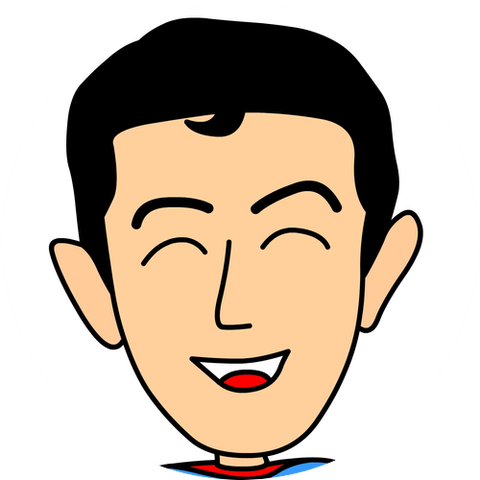 やまとマン社長
やまとマン社長今回は店舗ではなく、本部の査察で発覚したということですが、そのきっかけは、
①「内部告発」
または、
② あまりに分かりやすい「シールの二重貼り」による客からの通報だった。
と予想されます。②ならオーナーの指示だろうから、より罪は重いでしょう。
不正を生まないビジネスモデルと予防策
今回のような不正を防ぐためには、廃棄ロスそのものを減らすためのビジネスモデルを導入することが不可欠です。
ロス削減と利益を両立する「ツーオーダー」モデル
廃棄ロスを根本的に減らすためのモデルとして、弁当チェーンの「ほっともっと」やハンバーガーチェーンのマクドナルドが導入している「ツーオーダー」や「予約注文」があります。「ツーオーダー」とは、お客様からの注文が入ってから調理を開始する方式で、作り置きをしないため、常に出来立てを提供でき、廃棄ロスを大幅に削減できます。
「予約注文」もまた、ロス削減に大きく貢献し、人件費コントロールもしやすい有効なビジネスモデルです。事前に注文数を把握できるため、食材の仕入れや調理量を正確に調整でき、無駄な廃棄をほぼゼロにすることが可能です。
特にクリスマスケーキやおせち料理など、需要が予測しやすい季節商品で広く採用されており、最近では弁当などの日常的な商品でも、オンラインやアプリを通じた予約注文システムを導入する店舗が増えています。
かつて見込み生産での「作り置き(ビンストック)方式」だったマクドナルドも、2005年以降、注文ごとに製造する「メイド・フォー・ユー」と呼ばれる「オーダーメイド方式」に変更しました。その結果、商品廃棄量は導入前のほぼ半減となり、大きく利益に貢献し、健全な経営努力が実を結ぶ好例となっています。
厳格な監査体制による不正の予防
また、不正行為の発生を防ぐための予防策には、スーパーバイザー(SV)の役割が極めて重要です。SVらによる定期的な店舗監査や抜き打ちチェックが、不正の隙を与えないための鍵となります。
ミニストップには一般的な品質保証部という部署は存在せず、このことが今回の騒動を招いた一因とも考えられます。品質保証部とは、商品が安全・安心であることを保証するために、製造から販売までの品質管理を徹底しています。厳格な品質基準の設定、製造過程や流通段階のチェック、そしてお客様からの問い合わせ対応など、品質を維持するための活動を専門的に行う重要な部署と言えます。
品質やサービスは、お客様に対する最も重要な約束であり、ブランドの信頼性を左右するものです。今回のミニストップ騒動は、このお客様との約束をいかに守るかという点において、チェーン全体で取り組むべき課題を示唆しています。
これらの部署が連携し、店舗運営の隅々にまで目を光らせることで、現場を追い込まずに、不正行為を早期に発見・防止し、お客様からの信頼を守ることが可能になります。

フランチャイズの闇を照らす、信頼と本質への回帰
今回の不正を浮き彫りにしたのは、フランチャイズビジネスにおける本部と加盟店の間の歪みが一因と言えます。本部が一方的に厳しいノルマを課したり、現場の状況を考慮しないまま利益を追求する構造は、不正の温床を生み出す原因になります。短期的な利益ではなく、顧客に真の価値を提供し、従業員が誇りを持って働ける環境を築くという「本質的経営」への回帰が必要ではないでしょうか。
コンプライアンスは単なるルールではなく、顧客や社会との約束を守る「文化」です。
この文化を醸成するためには、経営層が倫理観を示し、従業員が「正しいことをする」のが当たり前だと感じられる風土を築くことが不可欠です。また、現場の声を聴く「傾聴」という経営手法は、従業員との信頼関係を築き、彼らが直面する課題を共に解決していく上で欠かせません。
真面目なオーナーが報われるために、今、必要なこと
ミニストップは、イオンの100%子会社でコンビニ業界第4位(約2,000店)という大きな企業です。しかし、今回の不正は、その規模に関わらず、フランチャイズオーナーの“十人十色”な事情と、それに伴う苦悩を浮き彫りにしました。真面目に経営を続けているオーナーさんにとっては、非常に切ない事案だったことでしょう。
本部と加盟店が『共存共栄』の実現を目指すためには、短期的な利益追求に走るのではなく、「人」(従業員やオーナー)を育て、「価値」(顧客への約束)を磨くことに注力することが重要です。この姿勢こそが、いかなる危機にも耐えうる強固な経営基盤を築き、安定経営に繋がる道です。
この記事は筆者が「LinkedIn」に掲載した「【ミニストップで“消費期限偽装”発覚!】」を要約、加筆したものです。




