【この記事で分かること】
売上を守り、事業を止めない。異常気象時代の店舗経営を支える、水害リスクマネジメントの決定版。
近年頻発するゲリラ豪雨や記録的短時間大雨は、店舗経営に甚大な影響を与えています。本マニュアルは、水害から大切な店舗、従業員、お客様を守るため、事前の予防策から災害時の具体的な行動計画までを網羅。ハザードマップ確認、止水対策、情報収集、顧客・従業員の安全確保、BCP策定など、事業継続のための実践的な対策を解説し、変化するリスクに対応できる「災害に強い店舗」を実現するための手引きです。
近年、日本列島は気候変動の影響で異常気象が頻発し、「ゲリラ豪雨」や「記録的短時間大雨情報」が日常化しています。短時間での猛烈な雨は都市機能に甚大な被害をもたらすことが増え、店舗経営における水害リスクへの備えは喫緊の課題です。
この「リスクマネージメント・危機管理マニュアル」シリーズ最新版では、激甚化する大雨災害から大切な店舗、従業員、お客様を守るための具体的な対策と、危機発生時の行動計画を分かりやすく解説します。
頻発する異常気象と店舗経営への影響
気候変動により、局地的な集中豪雨や線状降水帯の発生が常態化し、安全とされてきた地域でも浸水や河川氾濫のリスクが高まっています。
2025年7月10日、東京、神奈川、埼玉など1都8県で「記録的短時間大雨情報」が発表され、各所で100ミリ超の猛烈な雨を観測。道路冠水、アンダーパス浸水、河川氾濫危険情報発令、商業施設の浸水被害など、都市機能に甚大な影響が出ました。
このような大雨は、店舗への直接的な浸水被害や設備故障だけでなく、お客様の来店減少、従業員の出勤・帰宅困難、商品配送の遅延、さらには風評被害といった多岐にわたる経営リスクをはらみ、人命と財産を脅かします。これらのリスクを未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるための準備が強く求められています。
事前の予防策:浸水・水害から店舗を守る
大雨による被害を最小限に抑えるには、危機発生前の予防策が極めて重要です。
店舗の浸水対策の準備
1. ハザードマップの確認とリスク把握
自治体発行のハザードマップで、店舗地域の水害リスク(浸水深、河川氾濫、土砂災害など)を正確に把握し、対策の必要性を判断します。
2. 浸入経路と重要設備の特定
水の浸入経路(出入り口、窓、換気口、地下室など)や、電気設備・IT機器、重要書類などの設置場所を特定し、浸水時の影響を想定します。
3. 浸水対策用品の準備と設置確認
止水板、土のう、水のう、吸水シートなどを事前に準備し、いざという時にすぐに使えるよう、設置場所と方法を確認し、従業員間で共有しましょう。
店舗の浸水対策
1. 出入り口への止水対策
店舗出入り口には、土のうや水のう、軽量で脱着式の止水板・防水パネルなどを設置し、水の侵入を防ぎます。特に自動ドアや開放的なエントランス、路面より低い店舗では必須です。
2. 排水設備の点検と清掃
店舗周辺の側溝や排水溝、雨水ますにゴミや落ち葉が溜まると排水が滞り、冠水の原因となります。定期的な清掃と、排水設備の機能点検を怠らないようにしましょう。
3. 排水口からの浸水対策
キッチン、洗面所、トイレなどの店舗内排水口から、下水逆流による浸水が起こる可能性があります。大雨が予想される際は、水を入れたビニール袋などで排水口を塞ぐ、または専用の逆流防止弁を設置するなどの対策を検討し、店舗内からの浸水を防ぎましょう。
4. 高所への物品移動
床に置かれている商品や備品、重要書類などは、浸水した場合に使えなくなるだけでなく、避難の妨げにもなります。浸水リスクのある場所の物品は、棚の上など高い位置へ移動させておくことで、被害を最小限に抑えられます。
5. 電気設備・IT機器の保護と電源遮断
店舗の電気設備や機械室が浸水すると、停電や設備故障、さらには漏電による火災や感電などの二次災害のリスクが高まります。低い位置にある電気機器等は、止水板で保護するか、浸水の危険がある場合は事前に電源を遮断し、コンセントを抜くなどの対策を徹底しましょう。
6. 建物の補強
屋根や外壁は、強風を伴う大雨に耐えられる強度と防水性を持つことが重要です。必要に応じて専門業者による補強を検討し、床や壁も防水加工を施すことで、浸水時の被害を軽減できます。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼ることも有効です。
大雨警報発令時・被害発生時の対応と行動計画
「記録的短時間大雨情報」などが発表され、危険が差し迫った際には、迅速かつ的確な対応が求められます。冷静な判断と事前の計画に基づいた行動が、被害を最小限に抑える鍵となります。
正確な情報収集
信頼できる情報源から最新の気象情報を常に収集しましょう。「キキクル(危険度分布)」や河川の水位情報も確認し、状況の悪化を予測します。複数の情報源をクロスチェックし、正確な情報を得ることを心がけてください。
1. 気象庁
最新の気象情報、警報・注意報、ハザードマップを確認します。特に、大雨特別警報、洪水警報、土砂災害警戒情報、そして「キキクル(危険度分布)」で示される危険度をリアルタイムで確認することが重要です。
2. 地方自治体(防災情報ページ、SNSアカウント)
地域に特化した避難情報、避難所、ライフライン復旧状況などを確認し、店舗地域の具体的な状況把握に活用します。
- 例: 東京都防災ホームページ
- 例: 内閣府防災(X/旧Twitter)
3. ニュースメディア
テレビ、ラジオ、インターネットニュースサイトなどのニュースメディアは、広範囲の交通情報や被害状況を迅速に把握するのに役立ちます。全国ネットの民放ニュースサイトも活用しましょう。
- 例: 日テレ NEWS NNN
4. SNS(信頼できる公式アカウント)
公式SNSアカウントはリアルタイム情報に有効です。誤情報に注意し、公式マークのあるアカウントで真偽を確認しつつ、複数の情報源と照合しましょう。
- 例: 気象庁(X/旧Twitter)
顧客・従業員への情報発信と安全確保
営業状況の変更、休業の判断は速やかに行い、お客様や従業員にSNSやメール、店内掲示などでタイムリーに周知します。特に従業員に対しては、以下の点を明確に伝えます。
- 出勤判断: 警報レベルや交通機関の状況に応じた出勤の可否、遅延時の連絡方法などを事前に定めて周知します。従業員の安全を最優先に考え、無理な出勤をさせない方針を明確にしましょう。
- 帰宅判断: 大雨がピークを迎える前に、従業員の安全な帰宅を促す判断も重要です。公共交通機関の運行状況や道路の冠水状況を確認し、早めの退勤指示や、状況によっては店舗内での待機(備蓄品の確保も含む)を検討します。
- 安否確認: 災害発生時や帰宅後に、従業員の安否を確認できる連絡体制(緊急連絡網、グループチャットなど)を整備し、定期的に訓練しましょう。
お客様の安全対策
- 店舗内のお客様:店舗内にいるお客様に対しては、状況に応じて安全な場所(浸水リスクの低い高層階など)への誘導を行います。
- 避難誘導:避難が必要な場合は、明確な指示と避難経路を案内し、落ち着いて行動できるようサポートします。
- 幼児・高齢者対応:高齢者や小さなお子様連れのお客様、車椅子をご利用のお客様など、配慮が必要な方々への支援体制を整えておきましょう。
災害時対応と事業継続計画
1. 避難経路と避難場所の確認
洪水ハザードマップを確認し、店舗周辺の危険区域や避難場所、避難経路を事前に把握し、従業員間で共有しておきます。道路が冠水して避難が間に合わない場合は、建物の上の階へ移動するなど、状況に応じた判断が必要です。
2. 緊急時の役割分担とマニュアルの確認
大雨災害発生時を想定し、情報収集、浸水対策、顧客対応、除雪(大雨後の場合)など、従業員の役割を明確にしておきましょう。防災マニュアルに沿って行動できるよう、定期的な訓練を実施し、実効性を高めることが重要です。
3. 事業継続計画(BCP)の策定
大雨による影響を乗り越え、事業を早期に再開するための計画(BCP)を策定します。顧客と従業員の安全を最優先とし、取引先との連携、資金確保、重要データのバックアップなどを盛り込みましょう。万が一浸水した場合の清掃・復旧業者との連携も事前に検討しておくことが望ましいです。
変化するリスクに対応する経営のために
ゲリラ豪雨や記録的な大雨は、もはや「想定外」ではなく、店舗経営における「新たな常識」として捉えるべきリスクです。気候変動による異常気象の増加は、今後も避けられない現実であり、店舗経営者はこの変化に適応し、リスクマネジメントを強化していく必要があります。
本マニュアルで解説した事前の予防策と、大雨警報発令時・被害発生時の迅速な対応計画を綿密に立て、従業員と共有し、定期的に訓練を行うことで、大切な店舗、そしてそこで働く従業員や来店されるお客様の安全を守り、事業の継続性を確保することができます。
災害に強い店舗づくりは、お客様からの信頼獲得にも繋がり、持続可能な店舗経営の基盤となります。このマニュアルが、皆様の店舗における大雨対策の一助となり、安心安全な店舗運営に貢献することを心より願っております。
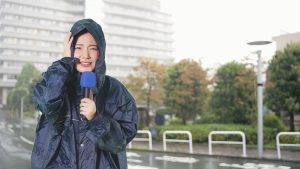



![[大雨対策]ゲリラ豪雨・記録的大雨・異常気象からお店を守る!水害リスク完全対策マニュアル 事業継続のため大切な店舗従業員やお客様を守る ハザードマップ確認、止水、情報収集、安全確保、BCPなど、予防策から災害時の具体的な行動の手引き](https://pbo-pbc.com/wp-content/uploads/2025/07/pixta_78206344_M.jpg)