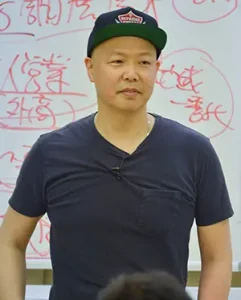【この記事で分かること】
部下との心の距離を縮め共感を生む、リーダーシップスタイルとリーダーの思考術。
リーダーシップにおける共感は、相手の心を完全に理解するのではなく、自ら歩み寄り、部下と同じ目線に立つ「行動」である。部下の興味の対象である「モノ」を介して会話を始めることで、部下は自己を深く探求する「遡行」が促される。これにより、部下はリーダーが自分を理解してくれていると感じ、強固な信頼関係が生まれる。
はじめに:部下に「任せる」勇気の、その先に
前回の『17.部下に任せて、結果を出すことは難しくない。【後編】』では、「部下に任せる」ことの重要性、そして「任せる勇気」と「丸投げ」の違いについてお話しました。
部下を信頼し、仕事を任せることは、リーダーの育成において不可欠なステップです。しかし、その「任せる」という行為が真に機能し、部下が自ら動くチームを作るには、もう一歩踏み込んだ行動が求められます。
それは、部下との間に「信頼」という強固な絆を築くことです。
「リーダーは部下の気持ちを理解するべきだ」とよく言われます。ただ、頭では分かっていても、現実には部下の感情の機微を察するのは難しいものです。
なぜなら、人間は完璧ではなく、他者の心を完全に理解することは不可能だからです。では、どうすれば良いのでしょうか。
今回は、リーダーシップにおける「共感」の正体と、部下との信頼関係を築くための「行動」に焦点を当てていきます。
共感とは、相手の目線に立つ「アクション」である
リーダーとして、自分の感情をコントロールすることはもちろん重要です。しかし、それと同時に、部下たち一人ひとりの感情も考慮し、その心に寄り添うことが求められます。
昔の武将が「人心掌握術」と呼んだもの、あるいは語弊を恐れずに言えば「人たらしの術」の基本も、やはり「共感」という行動にあります。
そう、共感は「行動」なのです。単なる「心から相手の気持ちになること」ではありません。超能力者(エスパー)でもない限り、それは無理な話です。多くのリーダーが「共感」を難しく感じるのは、この「他人の心を完全に理解する」という不可能なレベルを求めてしまうからです。
「いいから付いてこい!」と強引になってしまうのは、共感という行動のハードルを自ら上げてしまっている証拠です。
しかし、共感が「アクション」だと捉えればどうでしょう。ぐっと身近に、そしてやれそうな気がしてきませんか。
たった1分、いや30秒でも構いません。部下の話を聞く時間を作りましょう。リーダーのほうから部下に興味を持ち、歩み寄っていくのです。
例えば、昼休憩の時でもいいのです。
「そのカップ麺、初めて見たけど、どこで売ってるの?」
このように話しかけてみてください。相手も「新発売らしいっすよ。そこのコンビニで売ってました」ぐらいのことは答えてくれるでしょう。
この会話のポイントは、リーダーが「それ美味しい?」と聞いていない点です。
「美味しい/美味しくない」という主観を問う質問は、部下の価値判断を試されているように感じさせ、相手は身構えてしまいます。
そうではなく、事実で答えられる問いから始めることが、会話の地雷を回避する第一歩なのです。
「そんなこと話しかけても、『うぜえなあ』って思われるから…」と不安に感じるかもしれません。しかし、心配はいりません。
もしウザがられるとしたら、それはリーダーの態度に「上から目線」が残っているからです。
「おう、美味そうだな。どこで売ってんだ教えろよ」
このような、テレ隠しのような口調は、部下のガードを解くことができません。今の若い世代は非常に鋭いので、そうしたリーダーの心の機微を敏感に察知します。