
人材を「人財」に変える、逆境を成長の糧にする実践論
「人を大切にする」とは、甘やかすことではありません。むしろ、社員が自律的に成長し、高い生産性を発揮できるように、厳しさと愛情をもって育成することにあります。逆境は、社員が成長するための最高の教材となります。
経営理念の浸透と「エンゲージメント」の強化
社員を「人財」へと進化させる鍵は、経営理念を単なる額縁の言葉で終わらせず、日々の判断基準、行動基準として徹底的に浸透させることです。特に店舗経営においては、店長がこの理念の体現者となり、率先垂範することが重要です。
理念が浸透することで、社員は「なぜ、自分たちはこの仕事をしているのか」という問いに対する答えを持ち、迷ったときに正しい判断を下せるようになります。これが、組織と個人の間に強固な絆、すなわち高いエンゲージメントを生み出し、離職率の低下や、生産性の劇的な向上をもたらすのです。
失敗を恐れず挑戦させる「真の信頼関係」
挑戦には失敗がつきものですが、失敗から学ぶことで、人財はさらに磨かれます。経営者や店長は、結果ではなく、挑戦したプロセスや、失敗から得られた教訓を評価する文化を作る必要があります。
「失敗しても、会社はあなたを見捨てない。なぜなら、あなたは会社にとって最も大切な人財だからだ」というメッセージを、日々のコミュニケーションを通じて伝えることです。この真の信頼関係こそが、社員が安心して新しいアイデアを出し、常識にとらわれない行動を取るための土台となります。
現場の知恵を引き出す「学びの文化」の醸成
困難な状況を打破するヒントは、往々にして現場にあります。最前線でお客様と接し、最も効率的な業務プロセスを知っているのは、他ならぬ社員たちです。彼らが持つ「知恵」を経営に活かす仕組みが必要です。
たとえば、部門や店舗を超えた成功事例(ナレッジ)共有会、小さな改善提案をすぐに実行に移す権限委譲などが有効です。社員は、自分の意見が尊重され、それが会社を動かしていると感じることで、自己肯定感を高め、さらに積極的に「学ぶ」姿勢を持つようになります。この自発的な学びの姿勢こそが、企業が持続的に成長するための原動力となります。
まとめ:人を大切にする経営が、次なる「創意工夫」の扉を開く
「困窮に瀕する毎日にもめげず」に人本経営を実践することは、短期的には忍耐やコストを要するかもしれません。しかし、その先に待っているのは、いかなる逆境にも揺るがない、強靭で自律的な「個店経営」の実現です。
経営者や店長が「人」を最優先することで、社員は安心感を得、高いモチベーションとエンゲージメントをもって仕事で活躍します。その結果、顧客満足度は向上し、最終的には安定した売上と利益という形で、企業に還元されます。
この「人本経営」を通じて、社員一人ひとりの自発的な成長意欲が喚起されたとき、組織は次のフェーズへと進化します。それが、次回のテーマである商業経営の原理原則8.「学ぶことの基本『真似と創意工夫』」へと繋がります。
人を大切にし、現場からの知恵を活かす文化が醸成されることで、社員は「模倣(真似)」を単なるコピーで終わらせず、そこに独自の「創意工夫」を加えて、他社には真似できないイノベーションを生み出すようになります。次回は、この成長のための「学びの基本」について深く掘り下げますので、どうぞご期待ください。
-
【経営】-450x246-1.webp)
飲食店「繁盛の秘訣」5.飲食店の未来形。ECビジネスのはじめ方「銀座 ごち惣家」
-
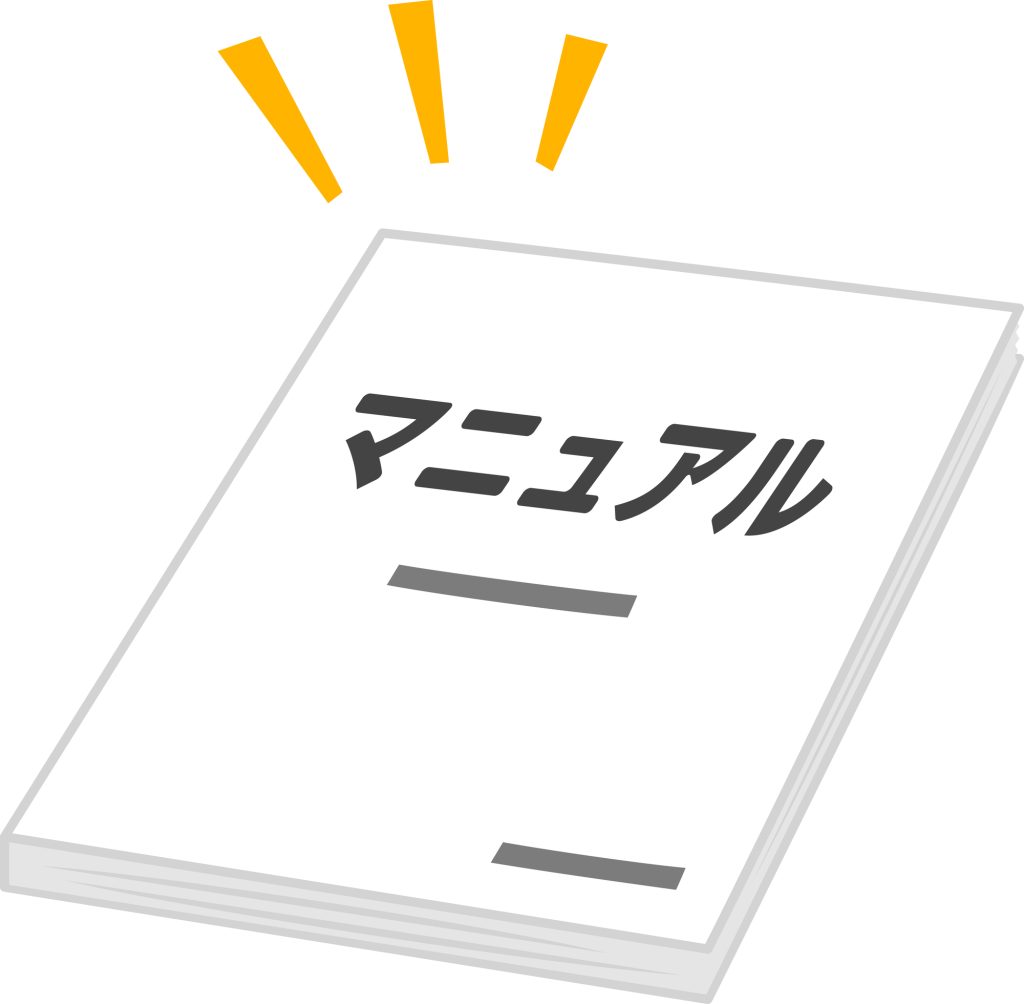
[経営Q&A]標準化・マニュアル化 – 職人気質のマネジャーにマニュアル化をしてほしいが動きません。どうすればいいか?
-

【最新版】店長マニュアル 2-3.損益管理(実践編)|数字を利益に変える、「儲かる」店舗の損益管理術
-

[経営Q&A]目標設定 – 目標設定の苦手意識を克服し、達成精度を上げる仕事術 目標達成の思考法と行動変容
-

【経営管理】店舗監査マニュアル 3-1.店舗監査の基本と分類|店舗の課題解決へ!監査の種類と目的別選び方を徹底解説
-

ポスティング集客入門 【目次】

