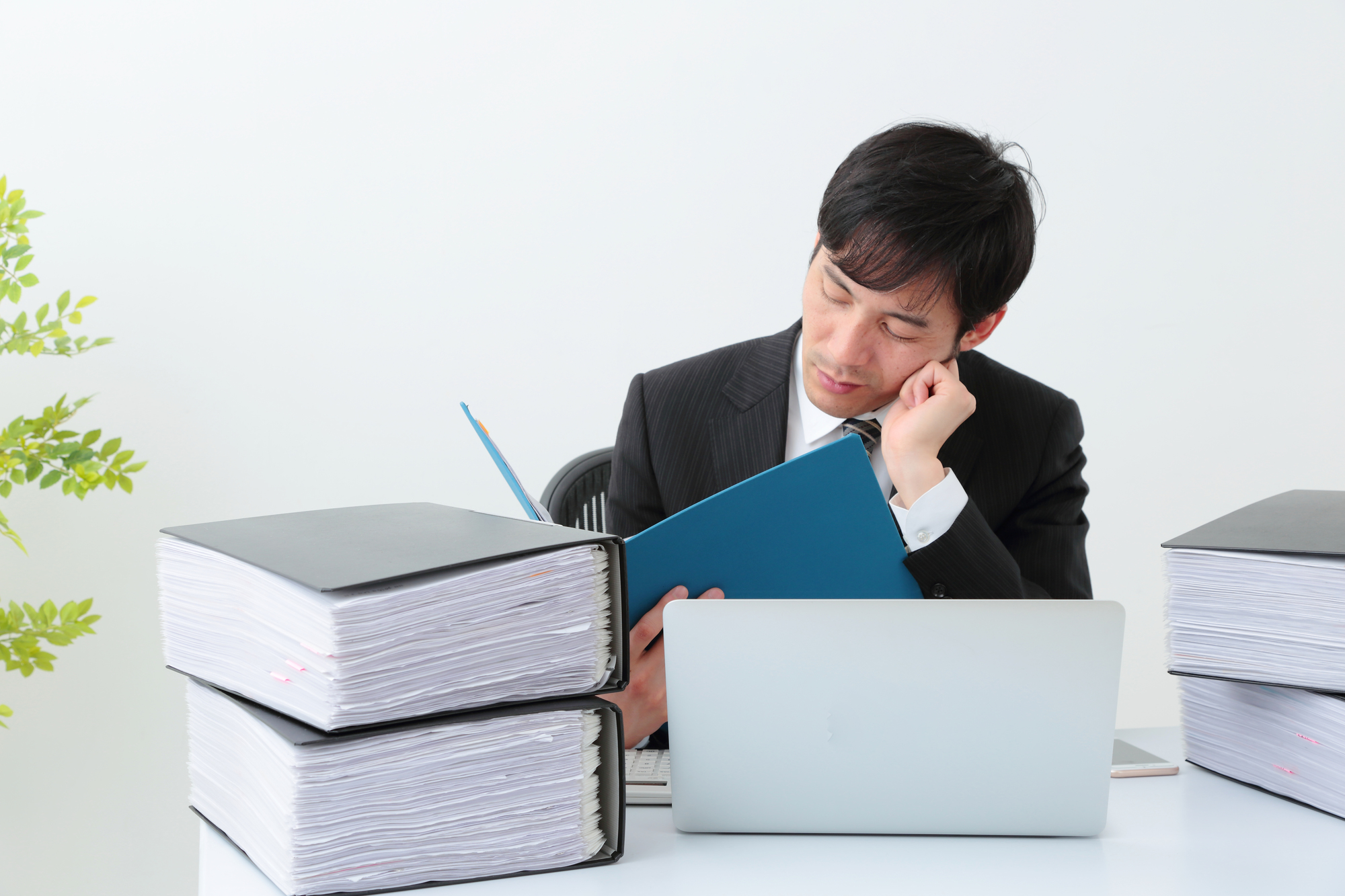【この記事で分かること】
マニュアル通りにしか動けないスタッフに悩んでいませんか?
本記事では、彼らがなぜ指示待ちになるのか、その根本原因を解き明かし、店長が実践できる具体的な育成手法を解説します。スタッフが自ら考え、行動できるサイクルを構築するためのノウハウが分かります。
(質問)
「我が社のスタッフには応用力がなく、指示されたことしかできません。指示待ちではない、自分で考えて行動できるスタッフを育てるにはどうすれば良いでしょうか?」
(質問の背景と趣旨)
店舗経営において、現場では予期せぬトラブルやお客様の多様なニーズに日々直面します。この時、マニュアル通りにしか動けないスタッフと、状況に応じて臨機応変に対応できるスタッフとでは、店舗のサービス品質や顧客満足度に大きな差が生まれます。
応用力のあるスタッフは、変化への対応だけでなく、新たな改善提案やアイデアを生み出す源泉にもなります。今回は、店長がスタッフの応用力を引き出し、自ら考えて行動できるチームを育てるための効果的なアプローチが求められます。
(回答)
スタッフの応用力を育むには、まず「応用力を阻害する原因」を理解することから始めましょう。主な原因は、「思考停止」と「失敗への恐れ」です。
・思考停止:なぜ自分で考えなくなるのか?
完璧なマニュアルや細かすぎる指示は、スタッフの思考を停止させてしまいます。自分で考える必要がない環境では、指示されたことをこなすだけの「作業者」になってしまい、応用力は育ちません。これは、指示を出す側のマネジメントスタイルに問題があるケースが多いのです。
・失敗への恐れ:なぜ行動に移せないのか?
失敗を厳しく咎められる環境では、スタッフは新しい行動を起こすことを避けるようになります。マニュアル通りに動けば失敗しないという安心感から、自ら試行錯誤する機会を失い、結果として応用力が身につきません。
(解決のポイント)
応用力を育む鍵は、スタッフが「考え、行動し、失敗から学ぶ」サイクルを回せる環境を作ることです。
1.「なぜ?」を問いかける習慣:指示を出す際、「なぜこの作業をするのか?」「この目的を達成するためには他にどんな方法があるか?」と問いかけ、スタッフに考える機会を与えます。
2. 成功体験を共有:小さな成功体験を共有し、正しく評価することで、次の挑戦への意欲を引き出します。
3.「心理的安全性」の確保:失敗を責めず、改善のためのフィードバックを行うことで、スタッフは安心して新しい行動に挑戦できます。
つまり、あなた自身の「マネジメントスタイル」と「コミュニケーションスキル」が重要になります。
これらは、応用力を育むための第一歩に過ぎません。「思考停止」と「失敗への恐れ」を乗り越え、自律的に動くチームを作るための具体的なトレーニング方法や、チーム全体を巻き込む仕掛けについては、「カクシンBLOG」で詳しく解説しています。