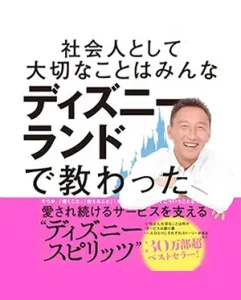【記事の概要】
指示待ち社員はいなくなる!ディズニー流「マニュアルなき究極の行動指針」の秘密
マニュアルのない現場で、ディズニーのキャストが自律的に最善の判断を下せるのは、創業者ウォルト・ディズニーの哲学が「心の指針」として深く根付いているからです。これは、細かなルールではなく、「いい組織や風土も意図して創る」という経営思想に基づき、従業員を自ら判断・決断できる「人財」として育成する仕組みがあるからこそ実現できるのです。
マニュアルを超えた経営のヒント
店舗経営や現場運営をしている皆さんは、マニュアルには書かれていない判断を迫られることが、日々たくさんありますよね。
予期せぬトラブル、お客様からの想定外のリクエスト、スタッフ間の問題…。その都度、「Aを選ぶべきか、それともBを選ぶべきか」と頭を悩ませることは、決して珍しいことではありません。
でも、ディズニーの現場では、従業員(キャスト)一人ひとりが、まるでマニュアルがあるかのように、迷うことなく最善の判断を下すことができるんです。なぜ、それが可能なのか?その秘密は、細かなルールではなく、すべての行動の根幹となる「究極の行動指針」が、従業員の心に深く根付いているからです。
今回は、僕がアメリカでの研修で体験したエピソードをもとに、現場の誰もが自律的に動けるようになるための「魔法の問い」と、それを可能にするディズニーの経営哲学についてお話しします。これは、現場を動かす店長や経営者の皆さんにとって、必ずや新たなヒントとなるはずです。
ウォルト・ディズニーの哲学が宿る「心の指針」
僕自身が現場で判断に迷う時、AかBか……。アメリカでの研修で向こうのトレーナーに質問をしました。
「現場で迷った時、何を基準に判断していましたか?」
すると、驚くことに、彼らと僕との答えが一致したんです。しかも、そう考えろって教わったわけではありません。全員が、自身の経験と感性から導き出した答えでした。
その答えとは、「自分の後ろにウォルト・ディズニーが居たら、どちらを選ぶのか」を基準にする、というものでした。
これは、マニュアルを暗記するのではなく、創業者ウォルトの想いを自分自身の心の指針として内面化しているからこそ出てくる答えです。ウォルトがパークを創った時の「大人も子供も一緒に楽しめる場所にしたい」「楽しくてきれいな場所にしたい」という純粋な想いが、日々の業務におけるキャスト一人ひとりの行動指針となっているのです。
この「心の指針」が従業員に深く根付いているからこそ、たとえマニュアルにない状況であっても、パークの世界観を壊すことなく、常にゲストにとっての最善の選択ができるのです。
なぜマニュアルは存在しないのか?「By Design(意図して創る)」という思想
じゃあ、なぜディズニーは、こんな「マニュアルなき行動指針」を従業員に浸透させることができたのでしょうか?その答えは、ディズニー社が元々映画製作会社であることにヒントがあります。
アメリカでの研修で、トレーナーは「By Design(意図して創る)」という言葉を何度も使っていました。
「いい組織や風土も、映画と同じで意図して創らなければ創れない。自然発生的に良い風土や良い組織にはならない」
この言葉は、細かな指示やルールを設けるのではなく、組織の土台となる哲学や風土を意図的にデザインすることの重要性を教えてくれました。
| 一般的な組織 | ディズニー流の組織 | |
|---|---|---|
| 行動規範 | 規則やマニュアルが中心 | 創業者の哲学が中心 |
| 行動指針 | 事例や前例に倣うことが多い | 普遍的な価値観に基づいて考える |
| 組織文化 | 自然発生的に生まれることが多い | 「By Design(意図して創る)」 |
| 従業員の役割 | ルールに従って動く人 | 哲学に基づいて自律的に動く人 |
| 育成の目的 | 均一なオペレーションの実現 | 自分で判断・決断できる人の育成 |
ウォルト・ディズニーは、ただの遊園地ではなく、「夢と魔法の王国」という世界観を創り上げました。その世界観を維持するためには、従業員一人ひとりがその価値を理解し、自律的に判断できることが不可欠です。
だからこそ、ウォルトの哲学をすべての行動のベースに置くよう、意図的にデザインされていたんですね。これは、店長や経営者の皆さんが自社の経営理念を浸透させる上で、非常に重要な視点と言えるでしょう。
誰もが「人財」へと成長する、ディズニー流・意思決定の仕組み
この「ウォルトの哲学」に基づく判断は、従業員の自己成長にも繋がっています。
会社から「あれをしなさい」とか「これをしなさい」と細かく指示されることはありません。しかし、現場では常に「チャレンジする機会」「気付く機会」「成長する機会」が与えられます。
- チャレンジする機会:マニュアルがないからこそ、自分で考え、行動する機会が生まれます。
- 気付く機会:お客様の反応や、自分の行動の結果から、何が正しかったのかを自ら学ぶことができます。
- 成長する機会:「ウォルトならどうするか?」という問いを通じて、自分自身の判断力を磨くことができます。
このように、ディズニーは従業員を単なる労働力としてではなく、自分で判断し、決断できる「人財」として育成する仕組みをデザインしているのです。
たとえどんなに教えても、教えられる側がその気にならなければ、成長には繋がりません。この仕組みは、従業員の内発的なモチベーションを引き出し、彼らが自ら成長したいと願う環境を作り出していると言えるでしょう。
まとめ:『マニュアルなき決断』が、組織を強くする
今回は、ディズニーがどのようにして従業員にマニュアルを超えた判断力を身につけさせているかをお伝えしました。その核心にあるのは、創業者の哲学を「心の指針」として共有し、良い組織や風土を「意図して創る」という経営思想でした。
この思想は、細かな指示に頼らず、従業員一人ひとりが主役となって輝く、強い組織を作り上げます。次回の記事では、この哲学がどのようにして入社初日から新人の心に深く刻まれるのか、その「新人歓迎の流儀」について掘り下げていきます。


-
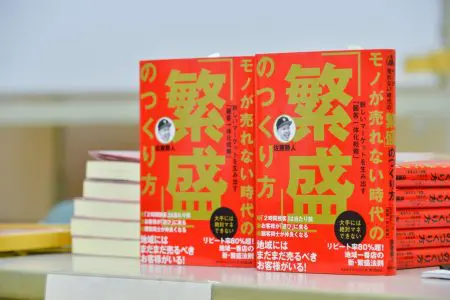
地域No1『サトカメ流』生き残り経営術 (第2回)サトカメ流人材教育論 その2学校で教わらなかった『元不良少年』を一念発起させたこと
-

6章 店舗集客と売上アップ『ストアレベルマーケティング・マニュアル』 5.ストアレベルマーケティングの正しい理解
-

【売上増大】店長マニュアル 2-7.店舗販売促進 効果的に売上を伸ばすマーケティングと販促の戦略と戦術|パート・アルバイトと共に売上を上げる
-

リスクマネージメント・危機管理マニュアル[防災・防犯]店舗セーフティ&セキュリティマネジメント
-

最新|アルバイト面接は15分で見極める!現場作業から解放し「稼げる逸材」を確保する店長の技術│募集・採用マニュアル 6. 面接
-

ドミノ・ピザとスターバックスに学ぶ 2.残暑厳しい日にドミノ・ピザ日本一号店がやっと完成した!