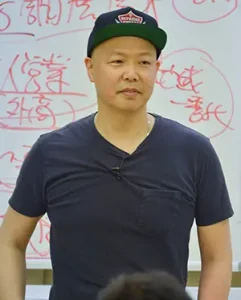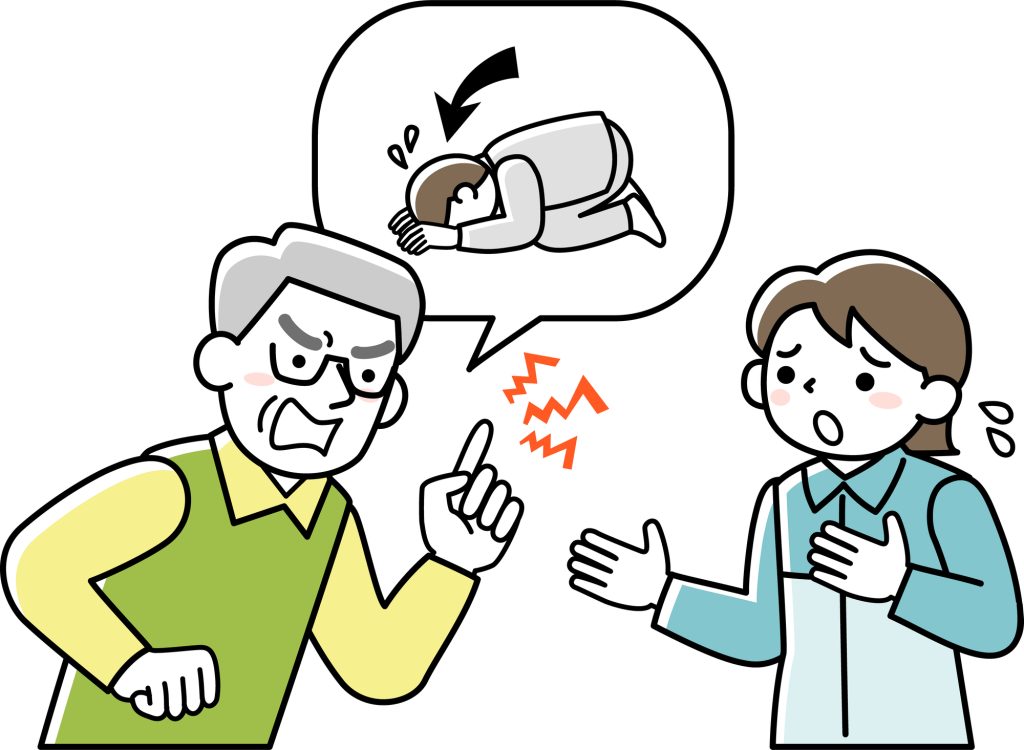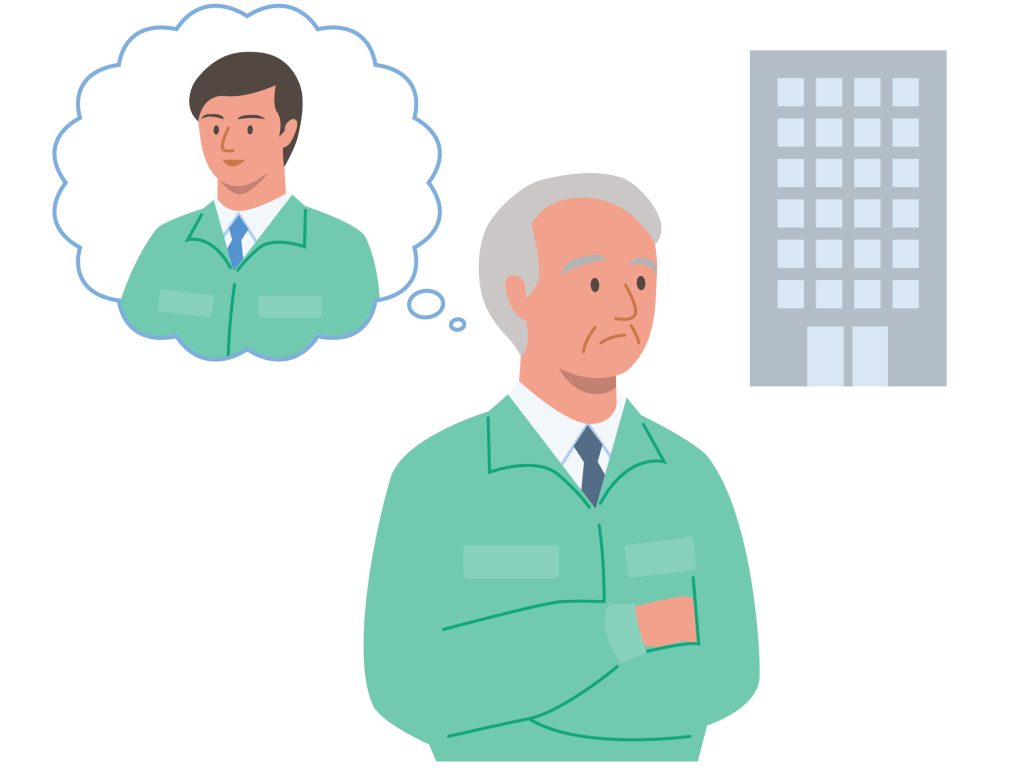リーダーの器を広げる「自己認識」のプロセス
蓋をしていた過去の感情に「真摯に向き合う」
前章で述べた「決着がつかないままの感情が何かしらあるのです。それを見つけましょう。」という課題を解決するため、特定の人にだけ感情的になってしまう原因を突き止め、自分の感情に正直に向き合うしかありません。
結局は、自分の感情がわからないと、相手に近付けないのです。私たちは、「自分で見えている自分のこと」の範囲でしか相手を見ることはできないという、人間の本質的な制約があるからです。
自分の内側を見つめ、過去に何があったのか、自分は何に傷つき、何を根に持っているのか。この自己認識なくして、相手の真の姿を理解し、歩み寄ることはできません。
「器」とは何か?自分の範囲内でしか相手を見られない人間の本質
「リーダーの器以上にチームは育たない」とよく言われます。この「器」とは、スキルや知識のことだけではありません。私が言う「器」とは、相手のことを見る力であり、それは突き詰めて言えば、自分のことをどれだけわかっているかに直結します。
自分の感情のバイアス(偏見)や、過去の経験からくるフィルターがかかっている状態では、部下を公平かつ客観的に評価し、育成することは不可能です。まずは自分を深く理解し、その器を広げることが、チームの成長の絶対条件となります。
【飲食店事例】過去の衝突から生まれた人間関係の溝を埋める
人手不足に悩むある飲食店の経営者は、忙しい最中にアルバイトに強く当たってしまうことが課題でした。特に、新人育成に失敗した過去を持つある社員に対しては、常に冷たい態度を取ってしまっていました。
彼は、その時の失敗が自分の「教え方の未熟さ」にあったにもかかわらず、社員の「理解力のなさ」に責任を押し付けていたことに気づきました。
その後、「あれは俺が教える順番を間違えたから、お前も困ったんだよな。今はもっと良い教え方ができるようになった。ありがとう」と伝えたところ、社員の表情が変わり、その後の業務への取り組み方が大きく改善しました。
究極の信頼を勝ち取る「アウトプットと謝罪」の瞬間
勇気をもって相手に「あの時のことだけどな」と話しかける
過去の捉え方が変わったら、できればそれを当の相手との間にきちんとアウトプットしたほうがいいと、私は強く推奨します。
「あの時こうだったのは、今になってわかったけど、こういうことだったんだな」
相手は「え?」とか「今更?」という顔をするかもしれません。しかし、臆さず話すことが重要です。これは、あなたが自分自身の過去の過ちを乗り越え、より大きな器を持ったリーダーへと成長した証を見せる行動だからです。
「あの時は悪かった、ごめんな」と言えるリーダーの強さ
客観的に見て、こっちに否があったと思うなら、究極の行動に出るべきです。
それは、「あの時は悪かった。ごめんな」と謝ることができたら最高です。
これは、リーダーの権威を失う行為ではありません。むしろ、真のリーダーシップとは、自分の非を認め、謝罪できる「人間的な強さ」に裏打ちされています。
謝罪したとき、相手は絶対にこう言うでしょう。「いやいや、僕のほうこそあの時はいっぱいいっぱいで。それで○○さんにそんな指示をさせてしまったかもしれません。すみませんでした」と。
これこそが、皆さんが部下の信頼を勝ち得た瞬間です。過去のわだかまりという名の鎖が断ち切られ、両者の間に本物の信頼と絆が生まれるのです。
まとめ:感情の氷解が導く、次世代リーダーシップへの道
前記事でリーダーシップの技術論や行動原則を学んだとしても、あなたの感情的なわだかまりが残っている限り、チームの潜在能力を最大限に引き出すことはできません。
本稿でご紹介したように、リーダーの器を広げるには、まず自分の感情と真摯に向き合い、過去の出来事に対する客観的な「捉え方」を修正することが不可欠です。
そして、最終的には勇気をもって部下にアウトプットし、「悪かった、ごめんな」と謝るという究極のアクションが、部下との間に揺るぎない信頼を築き上げます。感情の氷解は、組織の空気そのものを変え、受け身だった部下を能動的なチームメンバーに変貌させる起爆剤となります。
過去を乗り越え、感情をコントロールし、次世代のリーダーシップを発揮していく皆さんの奮闘をこれからも応援しています。
※専門家がお話を伺い、課題解決をサポートします。