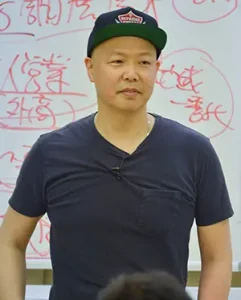あなたの「歩み寄り」が、部下の心を動かす
これまで一度でも部下に歩み寄ろうとして、拒否反応を示され、心が折れてしまった経験があるかもしれません。その気持ちはよく分かります。
しかし、もう一度だけ、心からその部下に興味を持って、同じ目線で話しかけてみてほしいのです。
なぜなら、その時、実は部下も同じように悔しかったはずだからです。リーダーが「シカトされた…」と傷付いたように、部下も「いい反応ができなかった」と歯がゆい思いをしています。
場合によっては、部下のほうがより深く傷付いていることもあります。
リーダーは「話しかけてあげた」という気持ちから入るため、その行為が拒否されたこと自体に傷付きます。しかし、急に話しかけられた部下は、うまく対応できなかった自分自身にダメージを受け、「この人との関係性を築けなかった」という残念な気持ちが、そのままリーダーへの苦手意識に繋がってしまうのです。
リーダーは、こうした部下の感情の機微まで考えられるようになりましょう。共感とは、「相手に興味を持つアクション」であり、その中身は「相手と同じ目線に立つ気持ち」なのです。
実践例:モノを介して、部下の「遡行」を促す
最初に部下に話しかける時は、モノを媒介にするのが最も効果的です。
例えば、部下が会社の支給品ではない、少しこだわりのあるシャーペンを使っていたとします。そのシャーペンをきっかけに会話を始めます。
リーダー:「そのシャーペンいいね。使いやすそうだね。どこで買ったの?」
部下:「どこだったかは覚えてないっすね」
リーダー:「なんでそれにしたの?」
部下:「前はこれだったんですけど、この部分がイマイチで。これがいいかなって」
リーダー:「ホントだ、ここがそうなってるんだ。いいね!これいくらぐらいしたの?」
部下:「○○円です」
リーダー:「そうか!それでその値段。いいね、私もこれにしようかなあ」
部下:「はあ(困惑した顔)」
このような会話の最初の「いいね」という主観的なポジティブ評価は、部下にとって自分の持ち物を褒められることになり、嫌な気はしません。
そして、最後の部下の「はあ(困惑した顔)」で終わったとしても、それでいいのです。その時は反応に困ったとしても、後日、リーダーが同じシャーペンを使い始めたら、部下は必ず嬉しい気持ちになります。
この行動のポイントは、「その場限りのテクニック」で終わらせないことです。モノに興味を持ち、実際に使ってみる。この一連の「アクション」こそが、真の“共感”なのです。
「遡行」:部下自身が自分に興味を持つきっかけを与える
上記の例は比較的スムーズに進んだケースですが、実際には「考えたこともなかった」という反応が返ってくることのほうが多いかもしれません。
「なんでそれにしたの?」と聞かれて、「使いやすいとか、考えたこともなかったです」と答えられるようなケースです。
しかし、それでいいのです。他者から問いかけられることで、部下は初めて「そういえば俺、これのどこが気に入って使ってるんだろう」と自分自身について考え始めます。
これは、精神科医療における「遡行(そこう)」という概念に似ています。人は、他人から問いかけられ、意識を過去に遡ることを促されることで、初めて自分自身の探求を始めるのです。
普通の人は、自分のことを深く研究していません。そこでリーダーが、「キミはどういう人間なんだ?」という本質的な問いを、「媒体を挟んで」投げかけるのです。
これにより、部下はリーダーからのコミュニケーションを受け入れやすくなります。そして、部下は自分自身の自己理解を始めたにもかかわらず、リーダーが自分のことを理解してくれているように感じるのです。
これが、「この人は俺のことを分かってくれる」という深い信頼に繋がっていくのです。
相手を理解するには、相手の歴史を知ることが重要です。しかし、今の時代に家族構成などを根掘り葉掘り聞くのは難しいでしょう。だからこそ、相手が使っているモノをきっかけに、そこから相手の歴史を聞いていくのです。
正直、面倒くさいと感じるかもしれません。すぐに本題に入りたいと思うでしょう。しかし、このプロセスを避けては、真の信頼関係を築くことはできません。
まとめ:共感は「行動」、信頼は「歩み寄り」から生まれる
今回は、部下との信頼関係を築くための「共感」というテーマでお話しました。
共感とは、単に相手の気持ちを想像するだけではなく、「同じ目線に立とうと歩み寄るアクション」です。モノを介したさりげない会話から始めることで、部下は自己理解を深め、同時に「リーダーは自分のことを分かってくれる」という安心感を抱くようになります。
次回は、リーダー自身の心にある「感情のわだかまり」に焦点を当て、それを乗り越えて真のリーダーシップを発揮するための方法を解説します。